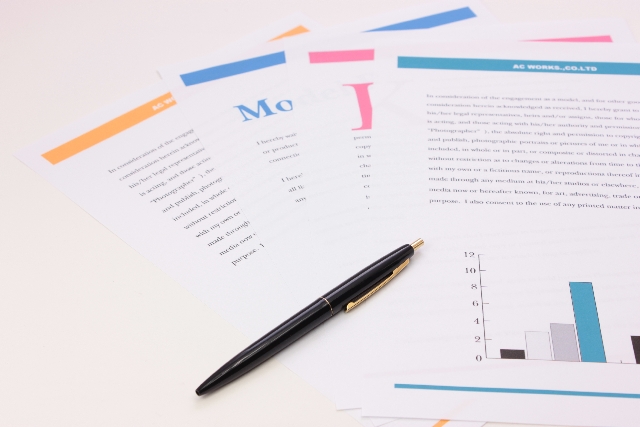


取締役の不当解雇の場合、退職金は発生しますか?
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。
ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。
解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。
解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。
不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。
裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。
どなたかご教示をお願い致します。
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。
ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。
解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。
解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。
不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。
裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。
どなたかご教示をお願い致します。
取締役を解任するのは取締役会ではなく株主総会の普通決議によってでないといけないでしょう。(会社法339条1項、341条)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もあります。定款はどうなっているのかですね。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。
>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。
>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。
>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。
従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。
>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)
株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。
>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。
>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。
>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。
従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。
>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)
株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
仕事を満期終了し、失業手続きをしてから、直ぐに次の仕事が見つかりました。
待機7日過ぎてすぐ内定になったため、説明会に出席していません。
ハローワークの方と相談し、説明会にでなくて
も問題ないと言われ、再就職手当の方法を聞きました。
しかし、就職先の条件が聞いていた話と違く、辞めたいと思っています。
再就職手当を貰う予定でしたが、貰わずに、通常通り失業保険を貰いながら仕事を探す事は出来ないでしょうか?
新しい会社の保険は来月5日からです。
年末調整の書類を渡してしまいましたが、返して貰った方がいいでしょうか
待機7日過ぎてすぐ内定になったため、説明会に出席していません。
ハローワークの方と相談し、説明会にでなくて
も問題ないと言われ、再就職手当の方法を聞きました。
しかし、就職先の条件が聞いていた話と違く、辞めたいと思っています。
再就職手当を貰う予定でしたが、貰わずに、通常通り失業保険を貰いながら仕事を探す事は出来ないでしょうか?
新しい会社の保険は来月5日からです。
年末調整の書類を渡してしまいましたが、返して貰った方がいいでしょうか
質問者さんは、ちゃんと失業保険もらえますよ、ただし最初3ヶ月は貰えないので、4ヶ月目でやっともらえますよ
私は今、失業保険受給者で、今週、第1回目の振り込みがあります。
で、次回の認定日までに、2回以上の求職活動をしなくてはならないのですが、
ハロワの就職支援セミナーだけでは、数が足りないので、やはりどこか会社の面接を受けるなり、書類を送ったりしなければならないのでしょうか?
失業認定申告書にはウソの申告
(求人している会社に書類送ったとか面接受けたとか)
したらバレますか??
ちなみに私は失業保険を全てもらってから活動しようと思ってます。
で、次回の認定日までに、2回以上の求職活動をしなくてはならないのですが、
ハロワの就職支援セミナーだけでは、数が足りないので、やはりどこか会社の面接を受けるなり、書類を送ったりしなければならないのでしょうか?
失業認定申告書にはウソの申告
(求人している会社に書類送ったとか面接受けたとか)
したらバレますか??
ちなみに私は失業保険を全てもらってから活動しようと思ってます。
私は受給中1度も求職活動なんてしませんでしたよ。特に聞かれたり書いたりすることも無かったので・・・。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
関連する情報